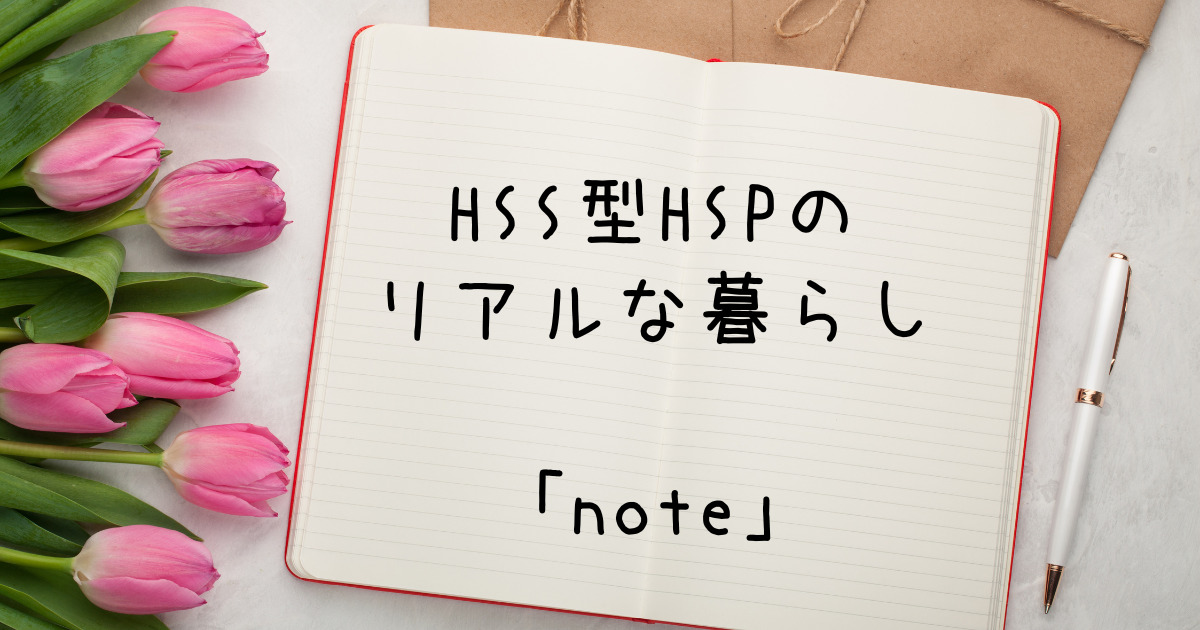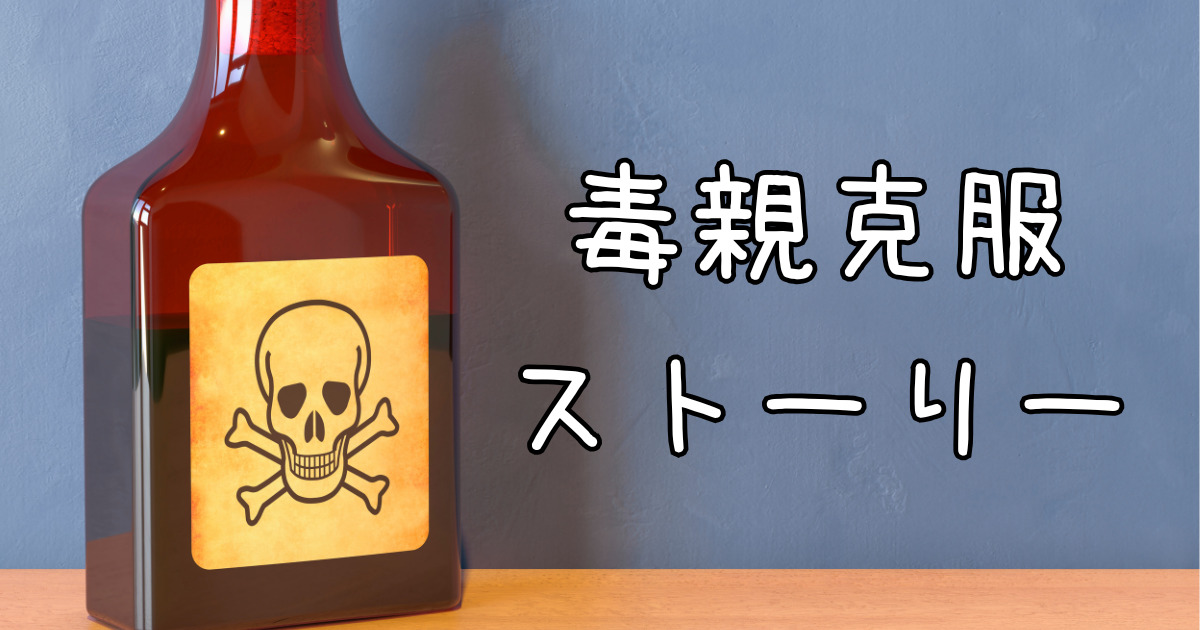投稿日:2025年10月13日 | 最終更新日:2026年1月31日
「うちの子、わがままなのかな?」
「どうしてこんなに育てにくいんだろう…?」
そう感じる瞬間があるなら、それはHSC(敏感すぎる子)からの見えにくいSOSかもしれません。
登校しぶりや癇癪、涙や無気力——。
子どもの「困った行動」の裏には、心の限界サインが隠れていることがあります。
HSCは、目に見えない刺激や気配にも反応しやすく、感情のキャパがすぐにいっぱいになってしまう子です。
今回の記事では、「見えにくいSOS」と、それに対する親の関わり方を探っていきます。
ただのわがままなのか、それともSOSなのか。
そんな迷いを抱えるママに、少しでもヒントが届きますように。
HSCの子が出す「よくあるSOSサイン」10選
ここからは、HSCの子がよく出す「10のSOSサイン」を見ていきます。
それぞれに、やってしまいがちなNG対応と、本当に子どもが求めている関わり方を添えました。
①登校渋りが始まる(でも毎回理由が違う)
登校前になると突然「お腹が痛い」「眠い」「気持ち悪い」と言い出す。
それなのに、毎回理由が違っていて、一貫性がない。
親としては「本当にしんどいの?」「また言い訳?」と疑いたくなることもあるかもしれません。
でもこの「理由が曖昧で日替わり」というところに、実はHSCの子ども特有のSOSの出し方が隠れています。
NG対応
「また?ちゃんと行きなさい」「昨日は行けたでしょ」
こうした言葉は、子どもを「行かせること」が目的になってしまっている状態です。
理由を説明できないまま、ただ「つらい」と訴えている子にとって、これは自分の感じている不調を否定される感覚になります。

共感されないと、傷ついてしまうんです。
HSCが本当に望んでいる対応
「理由はわからなくても、今つらいんだね」と、説明より先に「つらさ」を認めてあげる。
HSCの子は、環境の微細な変化(教室の空気感、先生や友達の表情、天気、身体感覚など)を敏感に感じ取り、それが「行きたくない」につながることがあります。
その感覚は、本人も言葉にできないことがほとんど。
だからこそ、言語化を急がず、安心して休める環境を整えてあげることが大切です。
「今日は心が疲れてるんだね」「まずはゆっくりしようか」
そう声をかけられるかどうかが、その子が「また歩き出す力」を取り戻せるかどうかを左右します。
② 癇癪や爆発が増える(特定の相手にだけ)
あるとき突然、激しく怒ったり、物を投げたり、叫んだり。
そしてその爆発が、決まって「特定の相手」に向かう。
たとえば家では怒りっぽいのに、学校ではいい子。
ママにだけ怒鳴るのに、パパには穏やか。
そんな「差」に戸惑った経験はありませんか?
実はそれ、「信頼してる相手にだけ出せる本音のサイン」かもしれません。
NG対応
「なんでそんなことで怒るの?」「いい加減にしなさい」など、怒っている様子の激しさばかりに気を取られてしまうと、「なぜここまでたまってしまったのか」という気持ちの根っこを見落としてしまいます。
HSCの子どもは、日常の小さな刺激や緊張を、知らず知らずに飲み込んでいます。
それが「怒り」という形で一気に噴き出すことがあるのです。
そして、いちばん信頼している相手にだけ、自分の限界を見せる。
それは、「ここなら出してもいい」と思えている証でもあります。

でも、「ぶつけてくる今」が、関係を立て直せるチャンスなんです。
HSCが本当に望んでいる対応
「外でがんばってるぶん、家では出せるんだね」
「安心できる人にしか出せない気持ちなんだね」
そう受け止められるとしたら、それは確かに「信頼の証」かもしれません。
でも実際には、その信頼を受け止める側は、傷つき、消耗しています。
HSCの子は、「外でいい子」の仮面を長時間かぶりつづけ、限界を超えると、もっとも安心できる人にだけ爆発します。
たいてい、それは母親です。
そしてその癇癪は、ただのわがままでも、感情表現でもなく、「もう限界なんだというSOS」です。
とはいえ、怒りや暴言にただ耐える必要はありません。
「爆発の奥にあるSOSに目を向ける」ことと、「親自身が壊れないように守る」ことは、同時に必要です。
- 子どもの怒りの裏にある「言葉にならない苦しさ」を想像する
- 必要であれば、専門家や学校とつながる
- 親自身も、安心して弱音を吐ける人を持つ
- 「一緒に整えていこうね」と、伝えつづける
癇癪を「我慢すること」と勘違いせず、「その奥にある叫び」に向き合うことが、親子関係を変えるきっかけになります。
ただし、癇癪を「相手にしないほうがいい」「放っておくのが一番」と考えるのは、とても危険です。
HSCの子どもにとって癇癪は、「助けて」がうまく言葉にできなかった結果の、身体ごとのSOS。
その瞬間に放置されれば、「やっぱり自分は、わかってもらえないんだ」と感じてしまいます。
その積み重ねは、自己否定や深い孤独感へとつながり、「もう何も言わない子」「気持ちを隠す子」へと変わってしまうこともあります。
③ 消えてしまいたい気持ちを口にする

「いなくなりたい」
「全部消えてしまいたい」
子どもがそんな言葉を口にしたとき、親は頭が真っ白になります。
どう反応していいか分からない。
けれど、ここで立ち止まるのではなく、動くタイミングだと捉えてください。
HSCの子がこの言葉を発するとき、それは「本当に消えたい」のではなく、「もうどうしていいか分からない」という心の限界サインです。
ここまでため込ませてしまうほど、がんばり続けていたということ。
そしてその我慢に、誰も気づいていなかったという現実です。
NG対応
「そんなこと言わないで」
「どうしてそんなこと言うの」
これは、親の不安から出る反応です。
でも、言葉を止めることは、SOSを潰す行為でもあります。
子どもは今、「もう無理だよ」と訴えている。
たとえあなたが「気を引きたいだけ」と感じたとしても、
それは「見逃していいサイン」ではありません。
「構ってほしくてイタズラする」のと同じ感覚で受け取ってしまうと、本当に必要な支援のタイミングを、見誤ることになります。
この一言をスルーされたとき、子どもは「もう誰にもわかってもらえない」と、深く絶望するかもしれません。
その声を否定すれば、
次はもう出してくれないかもしれません。
「怖くても、受け止める」覚悟が、ここでは必要です。
HSCが本当に望んでいる対応
「そこまでつらかったんだね」
「話してくれてありがとう」
たったそれだけでも、子どもにとっては「世界がひとりじゃない」と感じられる一歩です。
でも、それで終わりではありません。
この言葉を聞いた親は、必ず動くこと。
学校・医療・専門の相談機関、どこでもいい。
そして、このレベルのSOSが出たとき、親ひとりで対応しきるのは難しいこともあります。
命に関わる可能性がある状態に、家庭だけで立ち向かうのは限界があります。
迷ったら、学校のカウンセラー、児童相談所、自治体の子育て支援窓口、精神科・心理相談機関など、信頼できる第三者とつながってください。
「こんなことで相談していいのかな」ではなく、「早めに動いてよかった」ほうがずっといい。
子どもにとって一番の安心は、「大人が本気で守ろうとしてくれている」と実感できることです。
動くこと自体が、「あなたを本気で守るつもりがある」というメッセージになります。
「話を聞いてあげる」で止まってしまうと、助ける力を失います。
HSCの子は、親の「本気」を敏感に感じ取ります。
表面の言葉ではなく、行動の温度を見ています。
だから、怖くても迷ってもいい——でも、止まらないで。
このサインに出会ったとき、親にできることは「落ち着くこと」ではなく、動くことです。
安全な環境を整え、信頼できる人に相談し、子どもの世界を少しでも広げる。
それが、命を支える行動です。

「大丈夫だよ」と言うよりも、
「一緒に動くから安心して」と伝えてください。
それが、子どもに届く本当の支えになります。
④ 「どうせ自分なんか」と自己否定が強くなる
何かうまくいかないことがあると、
「どうせ自分なんかダメだし」
「自分なんて必要ないし」と、
自分自身を責めるような言葉を口にするようになります。
一見、ただの「ネガティブ発言」に見えるかもしれませんが、
これもまた、その子なりのSOSです。
心の中に積もった「傷つき」が、自分への否定という形で表れているのです。
NG対応
「そんなことないよ」
「もっと自信持って」
これは、善意から出た言葉でも、本人にとっては「わかってもらえない」と感じてしまうことがあります。
否定された気持ちはさらに心の奥に沈んでいき、
「やっぱり私はダメなんだ」と、深い孤独と無力感につながってしまうことも。

本当に、HSCは育てるのにコツがいるんです。
「普通の育て方」は、真逆にいくことがあるんです。
HSCが本当に望んでいる対応
「そう思っちゃうくらい、傷つくことがあったんだね」
と、理由ではなく「心の傷」に目を向けること。
HSCの子は、人一倍敏感で、空気の変化や人の言動を深く受け取ってしまいます。
「誰かに責められた」「無視された気がした」「笑われたように感じた」
その一つひとつが、心に刺さって離れず、やがて「どうせ自分なんか」「私なんていないほうがいい」と自分の存在ごと否定する言葉になって現れます。
このとき大切なのは、「根拠で説得する」のではなく、「気持ちを受けとめる」こと。
「そんなふうに思わせるくらい、つらかったんだよね」
「どんなふうに感じたのか、ゆっくりでいいから聞かせてね」
言葉を「打ち消す」代わりに、心の奥にある痛みを見つめる視点が必要です。

「自信がない」と言う子どもたちの多くは、
「自分がどう思われたか」を気にしているのではなく、
「自分という存在そのもの」に傷ついてきた子なんだよ。
⑤ 潔癖・こだわりが強くなる(不安をルールで抑えようとする)
「それ、さわらないで!」
「順番がちがう!」
「この服じゃないとイヤ!」
そんな「こだわり」がどんどん強くなってきたら・・・。
HSCの子にとって、「いつも通り」「安心できる状態」は、心を守る大切なバリアです。
ほんの少しのズレや変化が、強いストレスになってしまうこともあります。
もともと「キレイ好き」「整理整頓が得意」という性格の延長として、潔癖っぽい傾向がある子もいます。
でも、本人が「やらなきゃ」に追い詰められていたり、汚れや変化に強いストレスを感じているようなら、それはSOSのサインかもしれません。
「ここがズレてたらイヤ」「前と違うのが許せない」といった「こだわり」が、安心を保つための必死のコントロールになっていないか、
そっと見てあげてください。
NG対応
「そんなに気にしなくていいでしょ」
「汚れても死なないよ」
「いちいち面倒くさい子だな」
「それくらい我慢して」
大人からすれば「気にしすぎ」「神経質」と感じる行動も、HSCの子にとっては「身を守る最後の手段」だったりします。
ここで否定されたり突き放されたりすると、さらに世界が怖くなり、症状が悪化することもあります。
HSCが本当に望んでいる対応
- 「イヤだったね」「気持ち悪かったね」と感覚に共感する
- 「じゃあどうする?」と、次の行動を一緒に考える
- 「こだわり」を否定せず、「安心できる環境」を一緒につくる
- 「気にしすぎてるかも」と子ども自身が気づける余白を残す
安心を保つために必要なルールがあるなら、そのルールの中で安心できる道を一緒に探すことが大切です。
⑥ 持ち物をなくす/壊す/盗る(破壊・混乱型SOS)

物をなくす、壊す、盗る。
こうした「トラブル行動」の裏にも、実は言葉にならないSOSが隠れています。
一見「だらしない」「悪いこと」に見えるけれど、それが混乱や不安のはけ口になっていることもあります。
特にHSCは、自分の中にモヤモヤがたまっても、それをうまく表現できず、
「物にぶつける」「物を通して安心しようとする」ことがあります。
- 気持ちの整理ができず、筆箱をわざと壊す
- 不安を抱えたまま登校し、忘れ物や紛失が続く
- 寂しさを埋めたくて、誰かの物をこっそり持ち帰る(=万引きや「盗る」行動)
それは、「やりたくてやっている」のではなく、見つけてほしい痛みが、行動としてあらわれたのです。
NG対応
「なんでこんなことしたの?」「ダメでしょ!」
「盗みなんて最低」
「ちゃんと持ちなさい」「また壊したの!?」
こうした言葉で責められると、
「ダメな自分」「わかってもらえない自分」を、より強く刻み込んでしまいます。
HSCが本当に望んでいる対応
「何かモヤモヤしてたのかな?」
「さみしかった?」
「どうしてそんなことをしたのか、一緒に考えてみようか」
それは、「やりたくてやっている」のではなく、気づいてほしい心の叫びです。
行動の裏にある混乱や感情をくみ取ることが、HSCにとって最大の安心になります。
万引きや「盗る」行動が出たときは、特に注意が必要です。
家庭や学校での寂しさ・孤独・愛情不足が引き金になっていることが多く、
そのまま見過ごされると、より大きなトラブル(非行や引きこもりなど)へと発展してしまう可能性も。
だからこそ、「これはSOSかもしれない」と気づける目が、まわりの大人に必要です。
⑦ 友達を避ける/人間関係のトラブルが増える
「最近、ひとりでいることが多くなった」
「友達とトラブルが絶えない」
「もう誰とも遊ばないって言い出した」
そんな「交友関係の変化」が見られたとき。
HSCは人と深く関わりたい気持ちが強い反面、関係性に疲れやすいという特徴があります。
ちょっとした言葉や態度に傷つき、自己否定が加速してしまうこともあります。
それなのに大人が「仲良くしなさい」と関係の修復を急かしてしまうと、
「わかってもらえない」という孤独感がさらに強まってしまいます。
NG対応
- 「仲良くしなさい」
- 「気にしすぎじゃない?」
- 「相手の気持ちも考えなさい」
子どもは、すでに自分を責めています。
そこにさらに「悪いのはあなた」と言われると、自分を否定する気持ちが強まり、ますます心を閉ざしてしまいます。
また、「仲直りしなさい」と無理に関係を戻させようとすることで、「わかってもらえない」孤独と無力感が強く残る結果になることもあります。
HSCが本当に望んでいる対応
- 「何があったの?」ではなく、「どんな気持ちだった?」と感情に寄り添う
- 「それはイヤだったね」「そんな風に思ったんだね」と事実よりも「心の痛み」に共感する
- 「休みたいと思うなら、しばらく距離を取っていいよ」と「自分のペースで関わっていい」と伝える
- 「その子と仲良くなれなくても、あなたがダメなわけじゃないよ」と自己肯定感を守る声かけを意識する
子どもは、「関係がうまくいかない=自分に価値がない」と感じがちです。
だからこそ、人との関係に悩んでいる時こそ、「あなたはあなたのままでいい」という安心感が必要なのです。
⑧ 食べすぎる or 食べなくなる(過食・拒食傾向)

「最近、やたら食べる」
「全然食べようとしない」
それは、「食のわがまま」ではなく、心の不安や混乱が体を通して表れているサインかもしれません。
HSCの子は、ストレスを「感じすぎる」ほど感じ取ってしまいます。
頭では整理しきれない緊張や不安を、「食べる/食べない」という行動で表現することがあります。
これは、「助けて」と言葉にできない子どもが、唯一コントロールできる領域=「食」にしがみついている状態です。
NG対応
- 「またお菓子? ちゃんとごはん食べなさい」
- 「好き嫌い言わないの」
- 「そんなに食べたら太るよ」
こうした言葉は、「正す」「直す」ことに意識が向いてしまっていて、子どもの「不安な心」には届いていません。
行動だけを見てジャッジされると、HSCの子はさらに自分を責め、「また怒られる」「ちゃんとしなきゃ」と、ますます混乱していきます。
HSCが本当に望んでいる対応
- 「ちょっと疲れてるのかもしれないね」
- 「食べたくないときもあるよね」
- 「甘いものが欲しいってことは、エネルギーが切れてるサインかもね」
- 「最近、元気なかったけど今日はちょっと顔が明るいね」
こうした言葉には、共通点があります。
それは、「行動ではなく、“心”を見てくれている」という感覚です。
無理にバランスよく食べさせようとするのではなく、「何を食べたか」よりも「どんな気持ちで過ごしているか」に寄り添う視点。
その視点が、HSCにとっては「自分をわかってもらえた」という感覚につながります。
また、「いつも通りに食べられない自分でも、否定されなかった」という安心感は、自己肯定感の再構築にもつながります。
「食べすぎ」「食べなさすぎ」は、ただの「食の問題」ではなく、心のバランスをはかるシグナルとして出てくることもあります。
一見わがままに見える行動の中に、「急に変わった」「他の変化と重なっている」というサインが隠れていたら、それは「SOSの出し方がわからない」だけの状態かもしれません。

母は「食べろ」「残すな」とうるさくて、残すと罪悪感を植えつけてくるタイプでした。
愛情はくれないのに、食べ物だけは与えてくるから、私は食べることで自分を満たそうとしてた。
小学生の頃は太って、大人になってからは過食嘔吐が出るようになりました。
関連記事:HSPの私の「毒親克服」ストーリー
⑨ 無気力/だるい/「何も楽しくない」と言う
HSCは、見た目に反して「がんばりすぎている」ことがあります。
外では明るくふるまえていても、心の中では「疲れた」「動きたくない」がいっぱいになっていることも。
そんなとき、「何もしたくない」「楽しくない」と口に出せるのは、信頼してる人にしか出せないSOSかもしれません。
NG対応
「やる気出しなさい」
「そんなこと言ってちゃダメでしょ」
「だらだらしすぎ」
「せっかくの○○なのに」
「みんな楽しんでるよ?」
無気力状態のHSCに「やる気」を求めるのは逆効果です。
内側からエネルギーが枯渇している状態なので、言葉で鼓舞しても回復できません。
外から見えなくても、子どもの中ではすでに限界を超えてがんばった「後」であることも多く、「まだできるでしょ」は本人を追い詰めます。
HSCが本当に望んでいる対応
「ちょっと疲れちゃったかな」
「エネルギー切れちゃったのかもね」
「今日は『充電日』にしようか」
「何もしたくない日も、あっていいよ」
「がんばる時期を越えたから、体が止まってるのかもしれないね」
無気力さや「何も楽しくない」と感じる背景には、感覚過多・緊張・人との摩擦・がんばりすぎなど、HSC特有の疲労が溜まっている可能性があります。
本人すら気づかないまま限界を迎えていることもあり、無理に引っ張るより、「充電」を許す関わりが回復のきっかけになります。

私も、いまだに「頑張りすぎてエネルギーが枯渇したあとに、やっと気づく」ことがあります。
これはもう、特性なんですよね。
ずっと研究してきたからこそ、ようやく「そういうもんだ」と受け入れられるようになりました。
HSCにとっての「無気力」は、なまけではありません。
外ではがんばれていても、内側はすでに限界を超えていた…なんてことも。
「エネルギーが切れてるだけかもね」と声をかけることで、自己否定のスイッチを押さずにすみます。
⑩ 「〇〇買って」と執着する(物に安心を求める)

HSCが、「○○買って」と強く言うとき。
それが急に始まった場合も、いつも繰り返している場合も、実は「心のすき間」を埋めようとしているのかもしれません。
大人の目には、単なる「わがまま」や「甘やかされすぎ」と映るかもしれません。
でも、実はそこに心の不安やストレスが隠れていることがあります。
HSCは、強い不安やモヤモヤを感じたときに、「物が手に入れば、落ち着けるかも」と思ってしまうことがあるのです。
これは、「安心」を買いたいという感覚に近いかもしれません。
NG対応
- 「また?さっき買ったばっかでしょ」
- 「そんなもん、ダメに決まってるでしょ」
- 「わがまま言わないの」
- 「買い物依存になるよ」
こうした「正論」は、HSCの「不安」の根っこには届きません。
拒絶されると、「安心したかっただけなのに」と心を閉ざしてしまうこともあります。
外から見ると「ただの物欲」でも、中身は「心がぐらついてる」「不安でたまらない」という心の揺れの表現かもしれない。
大切なのは、「買う/買わない」の前に、その背景にある気持ちを見てあげることです。
HSCが本当に望んでいる対応
- 「最近ちょっと不安だった?」
- 「なにか心がざわざわしてるのかもね」
- 「そういう気分のときって、“何か欲しく”なるよね」
- 「欲しいって思う気持ち、ちゃんと聞いてるよ」
「欲しい」の奥には、不安定さ/安心の欠如/孤独感など、HSC特有の「心のぐらつき」があることが多いです。
とくに、安心基地が揺らいだときや、自分を保つのが苦しいときに出やすいサインです。
買ってあげるかどうかは、あとで決めればいい。
まずは、「買いたくなるほどの不安」があることに寄り添ってあげることが、何より大事です。
HSCが物を欲しがるとき、それは心のすき間を埋めようとするサインかもしれません。
本当は安心したい、満たされたい。
でもそれをうまく言葉にできなくて、「○○買って」と言ってしまうこともあります。
私自身も、愛情をもらえなかった子ども時代、ガラクタみたいな物ばかり集めていました。
物で心を落ち着かせたかったんです。

ガラクタで心を埋めてたなぁ…
親がつい言ってしまう「見落としワード」
「気にしすぎ」
「そんなに大したことじゃないでしょ」
「もっと強くなってほしい」
「疲れてるだけでしょ」
「〇〇ちゃんも頑張ってるのに」
これらの言葉は、親としては励ましのつもりでも、子どもにとっては「わかってもらえなかった」「自分の気持ちは受け入れられなかった」と感じることがあります。
HSCの子どもには、「一般的な『いい育て方』」が必ずしも合うとは限りません。
たとえば、よかれと思って伝えた言葉が、逆に子どもの自己肯定感を削ってしまうこともあります。
なぜならHSCは、「育てにくい子」ではなく、「雑に扱うと不安定になる子」だから。
- ちゃんと話を聞いてくれる
- 気持ちを尊重してくれる
- 安心できる場所がある
この3つがあれば、HSCは自分で気づき、自分で立ち直る力を持っています。

こう育ててほしかった。
こう言われて傷ついた。
あれはSOSだったのに、って今ならわかる。
だからこそ、今の子どもたちには、「見逃されないでほしい」って、心から思うんです。
不安を否定された子どもは、「さらに声を上げづらく」なっていく。
だからこそ、「受けとめる言葉」に置き換えていくことが、HSC子育ての第一歩です。
「HSC育てにくさ」と、「親の器」のミスマッチにより、毒親の連鎖が起こってしまった例を記事にしています。
じゃあ、親にできることって?

HSCの子どもは、「言葉にできない気持ち」を体や行動で表現することが多いです。
だからこそ、問題をすぐ「直す」ことに目を向けるのではなく、まずは、
- 「気持ちに名前をつけてあげる」
- 「安心できる雰囲気をつくる」
- 「『怒らないから大丈夫』と繰り返し伝える」
といった小さなサインキャッチと、安心感の積み重ねが大切です。
そして、子どもの異変は、親自身の不安や疲れのサインでもあるかもしれません。
「自分のしんどさ」も見つめ直すきっかけとして、いっしょに整えていけたら理想です。
なお、本記事で紹介した10のSOSサインは、ほんの一例です。
子どもが発しているサインに気づかれないままでいると、そのSOSはやがて内面や外側へと形を変えます。
- 内側に向かうと、自傷や引きこもりという形で。
- 外側に向かうと、万引き・喫煙・暴言など、いわゆる「非行」という形で。
どちらも、「本人の性格」や「しつけの失敗」ではありません。
ただ、どうしても言葉にできなかった、誰にも届かなかった「しんどさ」の、行き場のない現れなのです。
だからこそ、サインのうちに気づいてあげてほしい。
「わがまま」じゃなく、「助けて」の声かもしれない。
その視点で見つめ直すことが、子どもの未来を大きく変えます。
HSC自身が「自分をわかっている」ことが、最大の武器になる
娘がHSC(ひといちばい敏感な子)かもしれないと気づいたのは、赤ちゃんのころでした。
関連記事
ちょっとした物音にびくっとしたり、抱っこの仕方や空気の変化に敏感だったり。
「この子は、なんか違うかも」と思いながら、私自身も探り探りの育児でした。
そして、小学生になった頃。
私はまず、こう伝えるようにしました。

私自身がHSP(ひといちばい敏感な大人)なので、「あなたの気質はダメなものじゃないよ」と、同じ立場から伝えたかったんです。
あわせて渡したのが、『HSCの子育てハッピーアドバイス(明橋大二 著)』という本。
「HSCってなに?」
「どういう気質なの?」
ということを、まずは自分で「知る」ところから始めてほしかったんです。
自分のことがわかると、HSCはぐんと生きやすくなる

HSC(ひといちばい敏感な子)にとって、「自分がどう感じるタイプなのか」を知っていることは、それだけで大きな安心につながります。
外の世界に出れば、「我慢が足りない」とか「気にしすぎ」とか、否定されることのほうが多いです。
だからこそ、自分で自分を理解できていることは、揺るがない土台になります。
たとえば、
「大きな音が苦手なのは、耳がいいからだ」
「人混みで疲れるのは、感覚が敏感なだけ」
「怒られてすぐ泣くのは、怖がりだからじゃなくて、心が反応しやすいだけ」
そんなふうに、自分の「感じ方」をフラットに見つめられると、まわりと違っても怖くなくなります。

「あなたはそのままでいい」って、ちゃんと理由をつけて教えてあげたかった。
親にできるのは、「通訳」と「言語化サポート」
HSCの子は、自分の感じ方をうまく言葉にできないことがよくあります。
「なんかイヤ」「なんかモヤモヤする」「うまく言えないけど泣きたくなる」
そういう状態になると、大人には「わがまま」や「甘え」に見えることもあるでしょう。
でも、HSCは「伝え方がわからない」だけで、自分でもちゃんと理由がわからずに苦しんでいることが多いんです。
だから、親にできるのは「通訳」になること。
「大きな声にびっくりしたんだね」
「人が多いと疲れちゃうよね」
「今は泣いてもいいよ、ちゃんとつらかったんだもんね」
そんなふうに、子どもの気持ちを「言語化」して渡してあげると、子どもは「そうか、自分はこう感じてよかったんだ」と、少しずつ自己理解を深めていけます。
まとめ:SOSは「見ようとしなければ、見えない」
HSCの子が出すSOSは、派手ではありません。
泣き叫ぶこともあれば、ただ黙って消えていくようなサインもあります。
だからこそ、「見ようとする意志」がすべての始まり。
子どものSOSに気づけるのは、
誰でもなく、毎日そばにいるあなたしかいません。