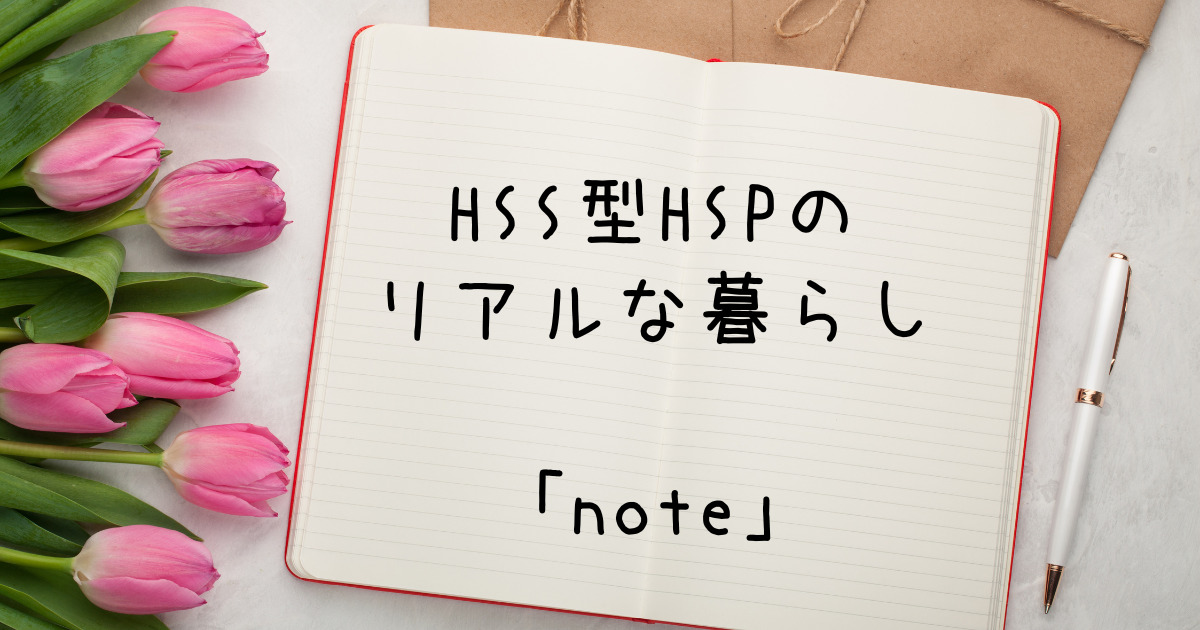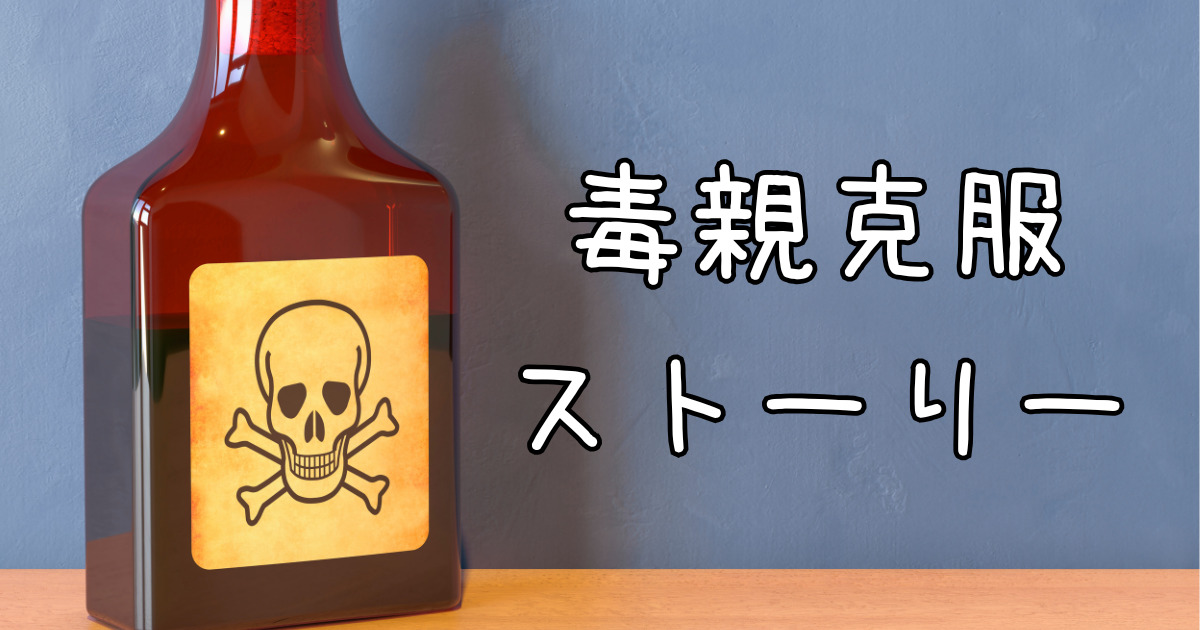投稿日:2025年10月18日 | 最終更新日:2025年10月18日
私は、サイコホラーが好きです。
でも、映像作品は無理。
ホラー映画を見ると、音や光、テンポの強さで心拍が上がってしまいます。
たった数分見ただけで(むしろ予告だけでも)、「あ、これ寝る前に引きずるやつだ」と察して停止ボタンを押してしまう。
それでも、怖い話や人間の闇には強烈に惹かれてしまう。
マンガでサイコホラー作品を読み漁ってしまう。
漫画アプリのコメント欄の、「この人の行動、母親との共依存が原因では?」といった考察を読むのが、最高におもしろいんです(笑)
作品そのものより、読者たちの「心理の読み解き合戦」が楽しい。
そして、恐怖そのものよりも「なぜそうなったのか」が気になる。
この「怖いのに惹かれる」矛盾を、ずっと自分の中でうまく説明できずにいました。
でも最近、「あ、これHSS型HSPの構造そのものかもしれない」と、気づきました。
HSS型HSPとは?
「HSS型HSP」って、最近よく耳にするけれど、たぶんこの気質を持つ人ほど、自分をうまく言葉にできずにいるんじゃないかな。
その矛盾を、少しでも整理してみたくて。
まずは、この「アクセルとブレーキを同時に踏むような脳の構造」から、覗いてみたいと思います。
アクセルとブレーキを同時に踏む脳の構造
HSS型HSPという言葉を聞いたことがありますか?
これは、刺激を求める「HSS(High Sensation Seeking)」と、刺激に敏感な「HSP(Highly Sensitive Person)」の両方の特性を持つ人のことです。
つまり、「刺激を求めるけど、刺激に疲れてしまう」。
アクセルとブレーキを同時に踏んでいるような心の構造です。
「HS型の衝動性」の例を挙げるなら、こんな感じです。
- 新しい世界を見たい
- 人間の心理や社会の裏側を知りたい
- 「普通じゃないもの」に惹かれる
一方でHSPの側面では、こんな傾向があります。
- 音や光、感情の刺激に過敏
- 人の痛みや緊張を自分のことのように感じる
- 情報を深く処理しすぎて疲れやすい
つまり、心の中に「もっと知りたい」という探究心と、「もう無理、疲れた」という防衛反応が同居しているのです。
このアンバランスさが、サイコホラーに惹かれるけど映像は無理、という現象を生み出しているのだと思います。
HSS型HSPがサイコホラーに惹かれる心理の分解

未知の世界を「知りたい」「理解したい」気持ちはある。
でも、全部を感じ取ってしまうと、自分の中が乱れてしまう。
知ろうとするほど、心が揺れてしまう。
そんな、HSS型HSPならではの「限界線」があるように思います。
感じすぎる心と、知りたい衝動のせめぎあい
サイコホラーを読むとき、私の中では常に3つの心が同時に動いています。
ひとつは「知りたい」という好奇心。
もうひとつは「感じすぎて苦しい」という繊細さ。
そしてそのあいだで、「理解したい」という心理的な知性です。
たぶん、HSS型HSPの脳は「理解欲求」と「感情共鳴」を行き来するようにできているのでしょう。
HSSの好奇心「未知を覗きたい本能」
HSSの「刺激を求める」傾向は、派手なスリルだけでなく、知的刺激にも向かいます。
「人がどうして壊れていくのか」
「どんな瞬間に境界線を越えるのか」
そういう「心の深層構造」を知りたくて、ついホラーのページをめくってしまう。
▼▼関連記事▼▼
でも、それは「怖いもの見たさ」ではなく、「理解したい衝動」に近い。
善悪よりも、「なぜそうなるのか」という「因果」に惹かれる。
たとえば、サイコホラーに出てくる加害者を単なる「悪」とは思えません。
だって、加害者は「かつての被害者」であることが多いから。
むしろ、「どんな人生を経てここまで壊れたのか」を知りたくなるんです。
その瞬間、私は恐怖を感じていません。
頭の中ではすでに「分析モード」になっているからです。
HSPの共感力「痛みをそのまま受け取ってしまう」

一方で、HSPの側面は、まるで感情のアンテナのようです。
登場人物の息づかいや痛みを、まるで自分の体で感じてしまいます。
映画で誰かが泣けば胸が詰まり、キャラクターがパニックになれば心拍数が上がる。
フィクションだとわかっていても、神経が「現実」として受け取ってしまうんです。
だから、映像作品は本当にしんどい。
音や表情、テンポ、すべてが感情移入を強制的に引き起こすから。
情報量が多すぎて、心の処理が追いつかないんです。
HSPは、目や耳から入る情報を「深く処理」する脳を持っています。
だから、感情や状況を一瞬で細部まで感じ取ってしまう。
それは鋭さでもあり、同時に苦しさでもあります。
心理理解欲求「闇を『俯瞰』で観察したい」知性
HSSとHSPが同居すると、「共感でのめり込む自分」と「分析で距離を取る自分」が交互に現れます。
たとえば、LINEマンガでサイコホラーを読んでいるとき。
悲惨な展開に胸がざわつくのに、同時に冷静な観察者の声が聞こえるんです。
「これは幼少期の愛着の問題では?」
「このキャラ、自己愛的防衛をしているな」
そうやって分析を始めると、不思議と安心します。
「感情」から「構造」へ視点が移動する瞬間です。
私にとってサイコホラーは、「恐怖のエンタメ」ではなく、人間理解のドキュメントに近いと感じます。
怖いけれど、知りたい。
見たいけれど、巻き込まれたくない。
HSS型HSPは、その「狭間」でバランスを取っているのだと思います。
「 好奇心 × 共感 × 繊細さ」の化学反応
この3つの要素が同時に動くと、脳がとても忙しくなります。
感情が過剰に動くたびに、思考が分析を始めて鎮火しようとする。
でも、分析しすぎると今度は「生々しさ」が戻ってきて、また揺れる。
だから疲れる。
でも、たぶんこれが「HSS型HSPの快」でもあるのだと思います。
危険なほど深い世界を、ギリギリの距離から覗く。
そのスリルの中で、「人間っておもしろい」と感じる。

映像作品がしんどい理由と、「間接鑑賞スタイル」の楽しみ方

映像作品の魅力は没入感ですが、HSP気質の人にとっては、それがそのまま負担にもなりやすいものです。
五感すべてを刺激されることで、情報処理が追いつかなくなる。
ここでは、私なりの映像作品と「ほどよく距離を取る」楽しみ方を話したいと思います。
恐怖を「笑い」と「分析」で中和する知恵
ホラー映画を観るとき、私がいちばん怖いと感じるのは幽霊や殺人鬼ではなく、感覚の洪水です。
- 音がドンッと鳴る瞬間
- 視界が急に暗転するタイミング
緊張を煽るBGMの波
あの「五感を一気に支配される感じ」が、HSPにはどうしても耐えがたいのです。
映像作品は「体験型」、文字やマンガは「観察型」
映像作品は、観るというより「体験する」ものですよね。
受動的に、容赦なく世界の中に放り込まれる感覚があります。
対して、文字やマンガは「観察する」スタイルです。
自分のペースで進められますし、怖くなったらページを閉じる自由もあります。
HSP脳にとっては、この「ペースを保てるかどうか」がとても大きなポイントです。
マンガや小説は、「感情の流入速度」を自分でコントロールできる媒体です。
だから、マンガや小説は感受性が高い人にとってはとても安全なんです。
「間接鑑賞」という安全な楽しみ方
私はよく、LINEマンガでサイコホラーを読みます。
でも、作品そのものよりもおもしろいのが、コメント欄なんです。
読者が投稿する考察やツッコミが、本当に深い。
「この人の暴走、母親との関係が根っこだよね」
「結局この作品って『共依存』の話じゃん」
そんな分析を読むたびに、「だよね!?」「私もそう思った!!」と、嬉しくなります。
怖さそのものよりも、構造を読み解く知性の連鎖が楽しいんです。
誰かが一緒に、丁寧に、おもしろおかしく(笑)分解してくれることで、その作品の闇が理解できるものに変わっていく。
自分が直接「恐怖体験」をしなくても、他の人の解釈を通して世界の裏側を覗ける。
それって、ちょっと離れた場所から光を当てるような感覚。
私にとっては、それがちょうどいい距離感なんだと思います。
ツッコミは、心の安全装置

それにしても、考察欄やレビュー欄のツッコミって最高ですよね。
「なんでそこでドア開けるんだよ!」
「誰も学ばない、だから毎回同じ事件が起こる。」
──そんな一言で、恐怖が一気にどこかへ飛んでいきます。
例えば、サイコホラーで超有名な「隣人X」は、他の漫画アプリだと私は刺激が強すぎて途中で挫折したのですが、回ごとに読者コメントが読める「LINEマンガ」では、マンガよりもむしろ、コメント欄が楽しみで読み続けています(笑)
ホラー作品って、そもそも知的好奇心が強くないと読まないジャンルなんですよね。
だからコメント欄も、ただの感想じゃなくて、ウィットに富んだ好奇心の塊みたいな分析で溢れてる。
それがまた、おもしろい。
笑っているうちに、脳が「恐怖モード」から「安心モード」に切り替わる。
HSP脳は感情の波に飲まれやすいですが、笑いが入ると一瞬でバランスが戻るんです。
ツッコミは、HSPにとっての緊急避難ボタンのようなもの。
恐怖を笑いに変えることで、心がパニックにならずに済みます。
しかも、HSS的な「知的刺激」はちゃんと残ります。
怖いのにおもしろい。
刺激的なのに安全。
ツッコミって、実はとても高度な心理的技術なんだと思います。
「レビューを読む」のが好きな理由
映画本編は無理でも、ホラー作品をおもしろおかしくレビューしてくれる人の投稿は大好きです。
淡々とネタバレを解説しながら、
「ここ、演出が天才」
「この監督、狂気の描き方が繊細」
といった分析が入ると、恐怖よりも創作としての美学を感じられます。
私のオススメは、こちらのレビューブログ。
ほんっとに面白いんですよ!!
とてもとても映像では見れないような作品を、面白く解説している(笑)
気になるけど見れない作品は、だいたいこちらのブログで楽しませていただいています。
HSS型HSPは、刺激の「質」さえ変えれば、深い世界を楽しめるタイプなんですよ。
「体験」ではなく、「観察」や「分析」に変換すれば、闇を安全に味わうことができます。
推しの世界観が、安全地帯を広げてくれる
私にとっての「安全に闇を覗けるスイッチ」は、推し(GLAYのHISASHI)の存在でした。
HISASHIはカルト映画やサイコホラーを「美学としての闇」として語る人です。
その姿に触れるたびに、
「闇って、こんなに冷静に、客観的に見つめていいんだ」
と思えるようになりました。
推しが「怖い世界」を安全に案内してくれる。
それは、私の中の理解したい欲求を肯定してくれることでもあります。
HSS型HSPにとっての「安全なホラー」とは、自分のペースを奪われない形で、闇を観察できる場のこと。
それがマンガだったり、レビューだったり、あるいは推しの世界観だったりするのです。
「怖いけど惹かれる」という感覚は、ただの矛盾ではありません。
「理解と共感のはざま」で生きている私たちにとって、
とても自然な反応なのだと思います。
まとめ 「怖いけど惹かれる」は矛盾じゃない

サイコホラーに惹かれるのは、人間の闇を「知りたい」「理解したい」という知的欲求があるからです。
でも、同時にその闇に触れると、共感しすぎて苦しくなってしまう繊細さも持っています。
それが、HSS型HSPという気質。
刺激を求めながら、刺激に弱い。
理解したいのに、巻き込まれるのが怖い。
この相反する感覚は、欠点でも弱点でもありません。
むしろ、「深く感じ、深く考える力」の裏返しなんだと思います。
私たちHSS型HSPは、「安全に狂気を覗く」ことができる稀有なバランス感覚を持っています。
その感受性は、他人の心を理解したり、世界の裏側を洞察したりするときに、きっと役に立ちます。
怖いけど惹かれる。
痛いけど知りたい。
その矛盾の中にこそ、
人間としての深さや、優しさが宿っているのだと思います。
そして、あなたにもきっと、「怖いけど惹かれる」ものがあるのではないでしょうか。
もしそれが人の心や物語の奥にある「闇」だとしたら。
それはあなたが「理解する力」を持っている証拠です。
無理して克服しようとしなくても大丈夫。
あなたのペースで、あなたの安全な方法で、その好奇心を、少しずつ味わっていけばいいと思います。